最新記事
2025.01.01
明けましておめでとうございます。
2024.12.24
【トライアル版】「IAUD 字幕CMアドバイザリーサービス」 が、テレビCMに起用されました!
2024.12.09
2006.03.12掲載

3月3日、シャープ幕張ビル(千葉県千葉市美浜区)の多目的ホールにおいて、「IAUD2005年度 活動報告・研究発表会」が開催され、来賓・一般59名、報道12名を含む284名の参加がありました。当日は、午前中に会員限定の「活動報告会」、午後に一般の方々も参加する「研究発表会」が開催され、会場の後方には各プロジェクト(PJ)やワーキンググループ(WG)、グループのパネル展示なども行われました。また、研究発表会終了後には「交流会」も行われ、参加者同士が相互の交流を深めました。


午前中は、会員限定による「2005年度IAUD 活動報告会」が行われました。最初に、後藤副理事長から挨拶があり、IAUDのこれまでの活動のまとめと、昨年11月に策定された中期ヴィジョン、再編された新部委員会体制への再編の趣旨などについて、説明がありました。

続いて、各WG・PJ・グループから活動報告が行われました。最初にワークショップWGの市場主査が登壇し、過去2年間、計2回に渡って開催した『UDワークショップ』について、目的や意義、これまでの成果、今後の展望や課題などについて報告がありました。成果については、ユーザーと会員間のコミュニケーションの場を提供できたこと、デザイナーの気付きや発見、工夫を導けたことなどを列挙しました。

次に、標準化研究WGの渥美主査から報告がありました。報告では、WGが当初から取り組んでいる、いろいろなジャンルに適用できる『UD評価マトリックス』について、作成の意義、具体的な内容と使用イメージなどについて解説があり、今後のスケジュールとして年度の後半にマトリックス表を公開し、10月の国際UD会議ではその成果を報告したい旨、説明がありました。

次に、労働環境PJの室井主査から、多人数・双方向のコミュニケーションである「会議」に着目して、2004年度から引き続き取り組んでいる「会議のユニヴァーサルデザイン」について報告がありました。報告では、2005度は月1回の月例会を通じて事例の研究や各種施設の見学、それに伴う情報収集などを行い、その成果として「会議のUDの3原則」を打ち出しました。

次に、移動空間PJの川崎副主査から、自動車の運転席の操作系(カーコックピット)のUDについて、プロジェクトの概要、活動の報告、今後の活動について、それぞれ報告がありました。その中で、今年度の活動報告としては、2005年8月にナビゲーション、オーディオ、エアコンに関する計18項目のアンケート調査、1月に実施したユーザーへのインタビューなどの内容が、報告されました。

午前中の活動報告会の最後に、事業企画グループ・アウォード担当の小島主査から、2005年度に試行審査を行った「IAUDアウォード(仮称)」について、報告がありました。世界のUDに関する表彰の実態調査、UDの評価方法などについてさまざまな角度からの検討を経て審査要領案をまとめ、試行審査を実施。結果としては、さまざまな業種・業態の企業・団体を一つの軸で評価することは難しく、来年度の本審査に向けてさらなる検討が必要との認識が示されました。

休憩を挟んだ後、一般からの参加者も加わり、「2005年度 IAUD研究発表会」が開催されました。冒頭、IAUDの戸田議長から挨拶があり、日本のUDの取り組みが世界各国から注目を集めた2002年の国際会議、2004年のブラジルでの国際会議を思い起こし、UDが今や日本の強みとさえ言えるという認識を確認。2003年に50歳以上が全人口に占める割合が過半数を超え、官民それぞれの取り組みが進み、UDが確実に企業・社会に浸透してきていることなどについて、話がありました。また、本年10月の国際会議を通して、日本の商品や社会にUDを定着させ、その文化・風土が日本発の形で世界に普遍していくことを期待として述べました。


続いて、経済産業省産業技術環境局企画官の渡邉氏にご登壇いただき、来賓のご挨拶をいただきました。その中で、渡邊氏は「IAUDの研究結果をこうした形で公表し、多くの方々が学ぶ機会を与えていただくことは、わが国のUDが加速する上で大変意味深いこと」と述べられ、研究発表会の意義を評価くださりました。また、経済産業省として実施しているUDの推進に向けた多様な施策について、紹介いただきました。特に、最近の取り組みとして1月に発表した「人間生活技術戦略2006」への取り組みについて資料を配布し、「社会ニーズ主導で技術を考えていく、新しいタイプの技術戦略」と説明されました。最後に、現在日本で起きていることは、今後アジア各国でも起きること、国際会議での世界へ向けてのUDの発信に期待していると述べられました。

次に、千葉県健康福祉部理事の亀井氏より、『県民参画によるアプローチ』と題した記念講演をいただきました。亀井氏は、千葉県の取り組みとして10年前の「千葉県福祉のまちづくり条例」策定、最近では当事者が発案者となった「ちばバリアフリーマップ」、ハードとソフトの両方に言及した「千葉県建築物ユニバーサルデザイン整備指針」、「ユニバーサルツーリズム」、「誰でも使えるホームページ コンテスト」など、さまざまなUD施策を進めてきたことを説明されました。また、その過程で、「健康福祉千葉方式」として、白紙の段階から当事者を含めて県民と行政が一体となって施策を検討する言わば「オーダーメイド型」施策への転換に取組み、「新たな地域づくり」への成果をあげていることを紹介いただきました。
次に2002年から着手した「心のバリアフリー」は、千葉県人権施策基本方針、PATS県民活動、障害者の差別に関する条例制定と歩を進めていることを紹介いただきました。PATS:Parking(駐車場)、Toilet(トイレ)、Seat(座席)。
最後にこれからのUDの取り組みと産業界に望むこととして、21世紀は「心の時代であり自己選択・自己責任の時代」、「新たに地域づくり」では県民が主役、そして、更なるUDを産業界との協力によって実現を目指したいと締めくくられました。

続いて、各WG・PJ・グループから研究発表が行われました。最初に、住空間PJの西田主査から、全く新しい空間の提案から、UDの解決方法、UDの着眼点を導くという逆周りの発想で研究に取り組んでいる、新空間チームの報告として、2004年度から実施した15件の事例調査の分析から、UD解決の工夫や考え方を分類整理し「機能性」「個別性」「社会との関わり(外部)」という三つのくくりと、6つの視点を導き、UD的な解決を引き出す可能性について言及しました。

次に、住空間PJ(エルゴチーム)の前田副主査から、浴室のUDについて発表がありました。浴室に着目してUD研究を進め、日本の「入浴文化の特異性」に着目することで今後へのヒント、新しい提案あるいは入浴文化の再構築が見えてくるのではないかとする発表がありました。今後は、「6つの視点」で評価しなおし、国際会議での新しい入浴文化の提案に取り組む予定と結びました。

次に、移動空間PJ(移動情報チーム)の武沢副主査から、移動における理想的な状態として、つなぎ目のない移動環境「シームレスモビリティ」の考え方を定義し、2005年度は東京駅や国際空港セントレアなどに出向き、実態調査と課題分析を行ったことなどが報告されました。また、発表の中で、想定した移動シナリオにそって、移動シーンをイラストや写真で映し出し、バス停や駅、改札、切符売場、電車の中などにおける不便さの課題と分析を解説しました。最後にシームレスモビリティを実現する解決策の提案の一例を示し、今後も引き続き取り組むと結びました。
次に、余暇のUD-PJ土屋主査と、松森氏から、発表がありました。まず、土屋主査からインドアチームの取り組みとして、「誰もが楽しめるホームシアター」をテーマに、チームとしてテレビ字幕に着目して調査・取材を重ね、その成果を冊子としてまとめたことなどが報告されました。次に、アウトドアチームの松森氏からは、駅とその利用者への調査を行い、その成果を駅の事例集にまとめたこと、望ましい駅のあり方として5つのコンセプトを作成したことなどが報告されました。
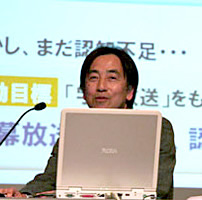
【写真16】土屋亮介氏 |

【写真17】松森果林氏 |

最後に、広報グループの酒寄主査から、IAUD会報におけるUDの取り組みについて、発表がありました。発表では、会報の制作を通して印刷物のUD化に取り組み、実際に適用している「IAUD会報UDガイドライン」の紹介がありました。読みやすいレイアウトや文字サイズ、フォント、図版率などの指標が示されています。また、「文字版面率」と「見やすいフォント」については、具体的な例示をして詳しく解説しました。
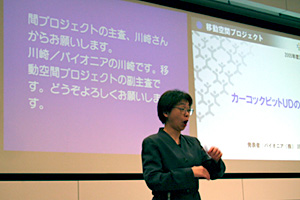

研究発表に続いて、川口理事長から、今秋京都で開催される「第2回国際UD会議」について、概要、行事内容、開催テーマに関する説明などのご案内がありました。また、募集を行っている論文について、幅広い人たちに参加して欲しい旨、呼びかけがありました。

また、会場の後方には、各WG、PJ、グループなどのパネルが常時展示され、昼の休憩時間には戸田議長が各ブースを回り、担当者の説明を受けました。さらに、研究発表会の後のコミュニケーションタイムには、多くの参加者が各ブースで、興味深そうに展示を見学していました。


その後、会場を3階の食堂に移し、交流会が行われました。交流会では、会員・一般の方々が多数参加し、UD関係者同士の親交を深めました。