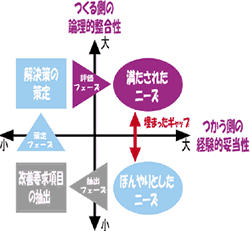IAUDの考えるユニヴァーサルデザインの理念構築に向けて
11月12日、大日本印刷研修会館(市ヶ谷)において、2004年度第4回定例研究会を開催し、53名の参加を得ました。
今回の定例研究会はそれまでのような講演会スタイルではなく、参加者による討議中心のプログラムとなっており、理念研究会WGのまとめた『UDの理念(仮説)』が議題となりました。
第一部《13時30分 ~ 14時15分》
はじめに、『UDの理念(仮説)』の発表にあたり、川原啓嗣IAUD専務理事より、「UDの歴史的背景・概要」、「日本の動向・世界の動向」、「IAUD設立趣旨・目的」、「IAUDが掲げる理念とは」について、資料を用いて解説がありました。
 写真2:川原専務理事による“UDの理念(仮説)”発表
写真2:川原専務理事による“UDの理念(仮説)”発表
「UDの歴史的背景・概要」では、「UDとは何か?」が、ロン・メイス提唱によるUDの7原則と、UDと類似した概念によって解説され、「日本の動向・世界の動向」では、各国のUDに関わる経緯、世界的にみたUDの現状について説明がありました。
「IAUD設立趣旨・目的」、「IAUDが掲げる理念とは」としては、国際UD会議2002のテーマ『人間(ひと)のために一人一人(ひとりひとり)のために』と、国際UD宣言2002およびIAUD設立趣旨について、また、これからのUDを考えていく上での超高齢社会という現状を踏まえておくことの必要性について解説がありました。
詳細は『UDの理念(仮説)』を御覧ください。
第二部 《14時30分 ~ 15時45分》
参加者それぞれが4つの分科会に分かれ、第一部で発表された『UDの理念(仮説)』について意見を述べ討議しました。

写真3:分科会形式による討議:グループ2
|

写真4:分科会形式による討議:グループ3
|
第三部 《16時 ~ 16時45分》
 写真5:討議による意見の公表:グループ1
写真5:討議による意見の公表:グループ1
分科会による討議から出てきた意見を代表者が参加者全体に公表しました。
代表的な意見は以下のとおりです。
- “目的”をもっとシンプルにはっきりと。
- “手段”と“活動”を分けられるのか? 理念は行動をイメージできるもの。
- “できるかぎり多くの人”=空白の部分が生じる。
- 主語が曖昧である。
- IAUDの属性、特性に沿った(意識した)表現にしたほうがよい。
- 使われていることばがUDではない。
- 生活者の視点を反映させるべきでは。
- 環境の要素を入れるべきでは。
- “視座”とは違いを認識することではないのか。
- IAUDは企業が多く参加している組織であるが、その組織の考える理念では、“教育”等の活動はどこに含まれるのか。
- トップランナー方式のUDをUD商品とするのか、それともギャップを少しでも埋めることができればUDか?
- “日本人のきめ細やかさ”という要素をUDに盛込むべきだと思う。
- 互いが共通して持てる理念にすべき。
- “できるかぎり多くの人”ということばに限界を意識してしまう。
- UDは商品だけなのか? 社会を作っていく運動であると考える。
- 理念についてIAUD会員以外への発信、情報収集、意見をいただく方法を考えるべき。
第四部《16時45分 ~ 17時》
今回の定例研究会の総括として、川原啓嗣IAUD専務理事より総評がありました。
今回は、会員による討議参加型というスタイルでの定例研究会でしたが、分科会討議では活発に意見交換が行われ、充実した研究会を開催することができました。
IAUDの考えるユニヴァーサルデザインの理念構築に向けて
(資料)IAUDの考えるUD理念仮説(フェーズ1)
UD理念研究フェーズ1で、現状のUDの考え方を整理します。
UD理念研究フェーズ2で、IAUDの発信するUD理念を考えていきます。
フェーズ1では、UDを考えるにあたっての「めざすところ」「視点」「立場の違いの認識」を共有します。
理念の文言
ユニバーサルデザイン(UD)とは、
(目的):できる限り多くの人が、それぞれのニーズを最適な形で満たすために、
(手段):「製品(ハード・ソフト)」「空間とその運用」「社会の規範や倫理」における、現状とニーズとの差(ギャップ)を、そこに係わるできる限り多くの人が継続的に改善することによって、
(活動):できる限り多くの人が社会に参加する活動である。
- UDがめざすところ(目的):できる限り多くの人が、それぞれのニーズを最適な形で満たす(視野)こと。《図1・図2参照》
- そのやり方(手段)
- ポイント1(視点):現状とニーズとの差(ギャップ)を継続的に改善すること。《図2参照》
- ポイント2(視座):立場を認識し、立場ごとに役割を分担すること。《図2参照》
(1)「製品(ハード・ソフト)」⇒「モノづくり」のフィールドのつくり手とつかい手の立場 ⇒メーカー、ユーザー等
(2)「空間とその運用」 ⇒「場づくり」のフィールドのつくり手とつかい手の立場 ⇒建築家やスペースデザイナー、ユーザー等
(3)「社会の規範や倫理」⇒「社会づくり」のフィールドのつくり手とつかい手の立場 ⇒行政、教育機関、市民(ユーザー)等
- その活動:できる限り多くのつくり手とつかい手が社会に参加すること。《図1参照》
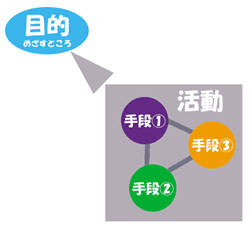
図1:目的/手段/活動の関係
|
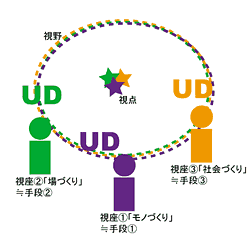
図2:手段の中身⇒視野・視座・視点の関係
|
「継続的に改善すること」とは、現実とニーズとのギャップを埋め続けること
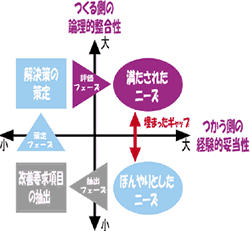 図3:現実とニーズのギャップの埋め方
図3:現実とニーズのギャップの埋め方
ギャップを埋める。⇒ぼんやりとしたニーズから、改善要求項目を抽出し、その解決策を策定し、解決策を改善要求項目に照らし合わせて評価する。《図3参照》
- ぼんやりとしたニーズから、改善要求項目を抽出する(抽出フェーズ)ときには、フィールドワーク等の調査の手法、日本人間工学会のUDガイドライン等の手法をつかう。
- そのときつくられた改善要求項目が、チェックリストになる。
- 改善要求項目から、その解決策を策定する(策定フェーズ)ときには、事例を参照したり、人間工学、人間生活工学、建築学、社会学等の知見をつかう。
- フェーズ)ときに、2のチェックリストをつかうことができる。
- その評価が○のとき、ぼんやりとしたニーズが満たされたことになる。
- そのプロセスを繰り返す。
理念とIAUD‐AWARDとの関係(参考)《図3参照》
明示/公開された「現実とニーズとのギャップを埋める」プロセスを、IAUD‐AWARDとして評価する。
理念と標準化との関係(参考)《図3参照》
抽出フェーズ、策定フェーズ、評価フェーズの3つのゆるいプロセスをガイドラインとして標準化する。そのフェーズの中は比較的自由にしておき、フェーズごとにつかえる手法を示しておく。
- 一般的に、今までのチェックリスト/ガイドラインは、改善要求項目から解決策の策定の間(策定フェーズ)でつかわれるものであった。
- そのような、案を策定するときのチェックリスト/ガイドラインでは、そのチェックリスト/ガイドラインにあること以外のアイディアが認められなかったり、つくり手の英知が発揮されなくなったりすることがおこる。
- 「できる限り多くの人が、それぞれのニーズを最適な形で満たすため」には、いつまでも理想を求め「継続的に改善する」ことが必要になり、そのとき、今までのチェックリスト/ガイドラインの考え方では、「継続的に改善する」ことが難しくなる。
- 「継続的に改善する」ためには、抽出フェーズでつくった改善要求項目をチェックリストとしてつかい、評価フェーズでそのチェックを行えばよく、そのとき、ぼんやりとしたニーズが満たされたかどうかが確認できる。
- 繰り返し3つのゆるいプロセスを行うことが「継続的に改善する」こと(スパイラルアップ)にあたる。
- 3つのゆるいプロセスとそこでつかえる手法を提示し、それを標準化と考える。
UD理念研究フェーズ2では、「視野(ニーズ)をもっと広げること」を考えていきます。